|
不定期便 第70号 013年3月10日 迷える物理学.2
ビッグバン宇宙誕生説 ―――013.2.22 |
発行 2013.3月10日 発行者 熊野宗治 |
|
| 一途な憶測の暴走 |
前号のことから、つまりわれわれの平和な空間は、現に体感し観測することのできるありふれた運動による以外の相対速度は持っていない。したがって静止し合ったもの同士でドプラー効果の生じないことは、もちろん実体験をして、たしかにわれわれはそれを知っている。しかし音について言えば、“風が吹いて”いれば別である。風上からの音は速く、風下からの音は遅く届く。音の媒質は空気すなわち風そのものだからである。
一方、宇宙では空気という媒質の代わりに、光を伝える媒質があって、その媒質が動いていないかぎり、相対速度を持たない物どうしはドプラー効果を生じない。
1915年から42年にかけて、アメリカの天文学者ヴェスト・スライファー(Vesto Melvin Slipher 1875~1969)の天体観測によって赤方偏移が発見された。もしも赤方偏移がドプラー効果によって生じているとすれば、星は猛烈な速さで後退しているはず、と彼は考えた。
1929年、アメリカの天文学者ハッブル (Edwin Hubble 1889~1953)は、遠い星ほど速い(赤い)ということから、すべての星が地球から遠ざかりつつあり、宇宙は膨張しているとする「ハッブル膨張則」を発表する。
という式で示された。Hはハッブル定数である。
ビッグバン宇宙誕生説は1946年、ロシアの科学者ジョージ・ガモフ(George Gamow 1904~1968)が言い出した説で、宇宙がいまも膨張しているとすれば昔ほど収縮してゆくことになり、宇宙がいまの10のマイナス28乗も小さい状態までさかのぼり、そのころビッグバン(大爆発)をおこして誕生したとする理論である。
それによれば、最初に1センチほどの玉(宇宙の卵)があった。それは高温高密度であり、熱核融合反応が起こる。最初に中性子だけがあって、中性子が崩壊して陽子と電子ができ、それら中性子、陽子、電子が結びついて重水素ができる。さらに爆発後三分、絶対温度10億Kに達するころ核融合によりヘリウム原子核ができる。これを説明するαβγ理論によればヘリウムまでで、それより重い元素はできないことになる。理論によれば原子核反応が起こって熱平衡に達すると、結合エネルギーの大きい鉄のような元素ができるはずだが実際の宇宙の元素組成では水素が主になっている。このことを説明するには温度が急激に下がるあいだに核反応が起これば熱平衡に達する前に核反応の進まない軽原素が多くできるからであるとした。高温状態は短時間であったことが必要で、ビッグバンは数分間の出来事であるというシナリオができた。熱い宇宙は膨張して冷え、バラバラであった陽子と電子は4000Kあたりで結びついて水素原子となり、3000Kになるとヘリウム原子核は電子を捉えヘリウム原子となる。爆発後40万年ころ、このようにして宇宙は晴れ上がる。これが宇宙ビッグバン誕生説の大要である。
| ドプラー効果が原因ではない |
そもそもの元であるビッグバンの卵がいかにして生じたのかは跳んで、現在、ビッグバン説が大手を振っている。その卵がいかに誕生したかは、まあ小さいことだからいいじゃないかというのか、誰も考えようとしない。しいて問いただそうとすると、マイナス時間と結合したような、ミンコフスキー時空とかいう話になって、ここまで来ては、バカじゃなかろうかと疑いたくなる。けれども、もちろん、小生のこの随筆を本気で本にしようと思うなら、文章はもっと当り障りのない穏やかなものに書き直さなくちゃだめだ。信奉者は少なくないし、ノーベル賞をもらった先生でさえ、まじめにビッグバン説を信じておられるくらいだから。
ところでもし宇宙膨張が赤方偏移の原因であるなら、おかしいことがたくさんある。前号の試論でも、光の媒質が運動していない限り、互いに静止した星たちの間でドプラー効果つまり赤方偏移は生じないはずであることを確認した。そしてまた、カフェでの観察によれば、静かな物と物との間に相対速度は存在しないことがわかった。物と物指が同じように膨張していれば、互いに相対速度は生じないからである。宇宙膨張がドプラー効果の原因になることはありえないことが分かった。
100歩譲って、もしも本当に星明りの赤方偏移がドプラー効果によるものなら、宇宙膨張ではなく実際に星~地球間の距離が離れつつあるほかない。夜空に見えるどの星も地球から遠ざかっているというのだから、彼らの広がり方の中心は地球でなければならない。全ての星が地球を中心にして後退運動をしていることになる。地球はそれほど奇跡の星であろうか?
ちがうちがう、絶対にちがう! 赤方偏移は別な原因によって生じているはずだ。
そこで考えられるのは、「電磁波は伝播の途中
| 光速不変の原理は正しいか |
光速不変の原理への疑惑
“空間”をどこに定めるべきかはとりあえず考えないことにして、いま青葉の繁った大木がすっくと立っている。この不動にみえる大地に対して風が吹いていれば、音はその空気中で約束どおりの音速を持つだろう。だとすれば、音が大地に対して音速を持つと考えるのは間違いということになる。
音の絶対座標(音が本来の速さで走る空間)は大地ではなく空気である。大地に置かれた机の上で音の速さを記述するためには、つまり大地を座標にして記述するためには、空気に対する通常の音の速さに、大地に対する空気の動きを加えなければならない。
しかし、大地と空気のどちらの座標で見ようと、音の本質的な物理現象――空気の振動と伝達――は同一のものであって、両座標において物理は同じである。仮に宙に舞う机を空想して、その机に置かれた画用紙に写生される音は舞うように描かれるかもしれないが、実際の音はそんなふうに舞ってはいない。
光は空間に対して光速を持つのであろうか? 音については空気がその絶対座標であった。光については空気に対してではないことだけは確かだ。なぜなら真空中でも光は走り、光速 c をもつ。現代物理学での光速についての認識は次のようだ。
地上で c である。気球に乗って空気つまり風と共に動いているときも c である。風よりも速い飛行機の中でも c である。なぜそう結論したかといえば次のようだ。
マイケルソン・モーレィの実験
もしある空間に対して光の速さがcだとすれば、その空間に対して動いている地球は、例えば太陽に対する公転速度υ=30㎞/secをもっている。
空間に対してcであるなら、地球上での光速は c +υや c -υと観測するはずである。ところが1887年アルバート・マイケルソン(A. A. Michelson)とエドワード・モーレィ(E.W. Morley)による実測――マイケルソン・モーレィの実験――に拠れば、いずれの方角についても c としか観測されなかった。(この実験は、一般には「エーテル理論を初めて否定したものとして知られている」と、今のわたしたちの知識からすれば、誤った解説がなされている。)
これについてアインシュタインが説明した《どんな運動をしている誰にとっても、光速は常に不変で c = 30万㎞/secである》というのが今も一般に認められている。これが相対論の元になっている。つまり光が速さcで走る絶対的な空間は存在しないとされている。光を見る誰にとっても、光の相対速度は存在しないとされたのだ。 (2月21日)
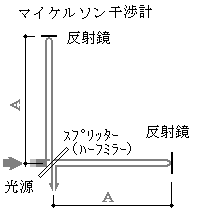
マイケルソン・モーレィの実験