|
�@�s������@��87���@014�N 1��7��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Θ_���ā@�R�@
�@�@�@�@���ʕۑ����������a�������e��邩 |
���s 2014�N1��7�� ���s�� �F��@�� |
|
�@�V�N���߂łƂ��������܂��B�g�}�g����̕s����ցh�͑�85�����瑱���悤���Ǝv���܂�

�@�W�T���ł́A��ΐÎ~��Ԃ́g���ׂẲ^�������Ԃ̑��a�h�ɑ��ė^������A�Ƃ��܂����B���̋�Ԃ͕��������������Ă��܂��B
�@�����͐g�߂ɑ��݂��镨�������̂ق��ɂ��A�F���S�̂̑��ݕ���F�߂Ȃ���Ȃ�܂���B���Ȃ킿�X�̕��̂����̉^���G�l���M�[�̐�Ηʂ����̉F���̂��ׂĂ̎������ɑ��Ă������Ƃɂ���A�ԈႢ�Ȃ��ۑ������i�ʂ��ω����Ȃ��j��Ԃł���A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()
�@���̍l�@�ɍۂ��āA�Ȃ��F���S�̂ɂ��čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����܂��ƁA�a�����đ��݂��镨���̑��v�ɉߕs����������Ƃ�����A�a���̑O��ŕ���(����)�ۑ��̖@��(���̑S�ʂ��s�ςł��邱��)�ɒ�G���邱�ƂɂȂ邩��ł��B
| �V�n�n���ɂ��@���͓K�p����� �@�@�@�@�@�@�@�@ 013.11/6 |
�F���������ɒa���������ɂ��Ă͏�������܂��B�_�ɂ��V�n�n���A�c����͕����w�ŋ���������e�ɂ���܂���B�_�w�҂ɂ͎����邩���m��܂��A�_�͓V��ɂ܂��܂��Ƃ������A�l�Ԃ̑z�����ƌ����Ă悢�ł��傤�B�������A�l���_�Ƃ��Ĉ��̂́A�l�q���鉽�҂������̉F���ɂ͂���ƒ������Ă��邩��ɂق��Ȃ�܂���B
�@��ɐ������A���҂ɂ��U��邱�Ƃ̂Ȃ��A���̑厩�R�̌��܂育�ƁA���R�@�����邢�́A������i���Ă��鑶�݂̂��Ƃ��A�킽���͐_�ƌĂԂɑ����������̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�l�ނ͎��R�@���Ƃ������̂��A�����܂Ō����Ɏe���K�v������܂��B�������܂��A�@���̂��Ƃɑ���ꂵ���̂ł�����B

�����̐��E�ł́A���]�̗D�ꂽ�l����ɒ��_�ɂ��邩����S���Ă����܂��B���������������ƂɁA�Ƃ��ɂ͌ł��J�Ō��ꂽ�A
�@ �������A�n��̐l�ƌĂ�ł͂����Ȃ��A�Ɠ`���҂͐\���܂��B�Ȃ�قǁA�܂��Ƃɒn��̕��͂悭�߂��A�߂Ɖ��߂邱�Ƃ�����܂���B�ʔ������ƂɁA��d�̉߂���Ƃ�����̂́A���ЂƂ��ʎq�Ƃ��������Ă��鐫�����̂��̂ł���܂��B�͂����茾���邱�Ƃ́A���ЂƂ͐_����^��������̂ł͂���܂���B�l���l�ɂ���āA�ނ�ɓs���̂悢�`���Ƃ��āA�l�ɗ^�����邾���ł��B
�@�_�łȂ��킽�������́A���낢��ȉȊw�I�ΏۂɁA����Ђ�߂�������l���̂ЂƂĂ͂߂Ă݂āA�ǂ̏ꍇ�ɂ������Ɋׂ�Ȃ��Ȃ�A������x���̌��t�������Ǝv����K�����̂��Ƃ��A���Ȃ��Ƃ������̂��������R�@���Ɨ������Ă����Ă悢�͂��ł��B���̊ԁA�������Ă悢���ǂ������A��ɓV�ɖ₤�̂ł��B�ԈႦ�Č��Ђɖ₤������ɁA�^���������Ă��炦�Ȃ����Ƃ����邩��ł��B
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�w�E�̏����̒��ŁA����͈Ⴄ�ł��낤�Ǝv���邱�Ɓ\�\�킽�����v���̂ł����\�\�������Ă݂����Ǝv���܂��B
�@���q�Ɨ��q���o����ď��ł���B����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���ł������̂������ɍĂё��݂�����ł��傤���H�g�Ăсh�łȂ��Ă��ł����B�g�����m�h�͂������A�g���ł������m�h�́A���͂�o����Ƃ�����܂��܂��ɁB
�@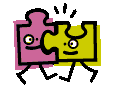
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ŋ߂̃m�[�x���܂ɂ��A���q�����ɁA���Ƃ��琶�܂ꂽ�����̗��q�����ʂ�z��B����Ȃ��Ȃ��Ƃ��������ł����I�@���l�Ɏ��ʂ�^������قǂ̗��q���A�����ɁA�Ȃ��A��ɂȂ��Ēa��������̂ł��傤���H�@
�r�b�O�o���F���a�����B����Ȃ��Ƃ����蓾�܂��܂��B��͌n�̖c���E���k��̔����Ȃ番����ʂ��Ƃ�����܂��c�B
120�����N���Ȃ��̐������t���������A�F���c�����_�ɂ��A�r�b�O�o�������̏�Ԃ����̐��̊ώ@����Ŏ�ł���B�Ȃ�قǁA��������̂�120���N�O�̎p�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł����A�����I�C�}�W�l�[�V�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ƃ��e���Ȃ��Ƃł��傤���B�ł́A���ܖ]�����Ō����Ă��邠�̐��̌��͂P�Q�O���N���O�ɐ�����o���͂��̌��ŁA���̂���͂܂��r�b�O�o���̒��S�t�߂ɂ��������ƂɂȂ�܂��B�܂蒆�S�t�߂���o���͂��̌����A�n�����P�Q�O�����N���O���̊O���t��(�]�����͂��̕����Ɍ����Ă���܂�)���瓞�B���Č����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���͂ǂ�Ȍo�H���o�Ă����̂ł��傤���H�@
�@�@�@�@�@�@�@�@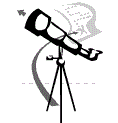
�@�����s�ς��܂��A���蓾�܂��܂��B�Ȃ��Ȃ�A���͂��Ƃ����L���ȑ��������Ǝ����Ŋϑ�����܂����B���Ƃ����m���Ȓl������ꂽ����ɂ́A����͉����ɑ��鑬���ɂ���������܂���B���̌����ǂ��𑖂�̂������߂Ȃ��ň�C�Ɂg�s�ς��h�Ƃ͂���܂�ł��B�Ȃ�قǒn���͑��z�ɑ����]���Ă��邩��A�n��Ō�������͕����ɂ���Ĉ���Ă݂���ɂ���������܂���B�����l����̂͂����Ƃ��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ϑ����ʂ͂ǂ̕����ł����������������Ƃɋ����āA�����āA�Ƃ��Ƃ����L���Ȃ���l�̈ӌ��ɂ���āg�����͕s�ρh�ƌ��߂��Ă��܂��܂������A�n�����̂��G�[�e���������Ă���̂�������Ȃ��ƁA���̂Ƃ��Ȃ��l���Ă݂Ȃ������̂ł��傤���H�@�G�[�e�������z�ɑ��ĐÎ~���Ă���Ɖ���ł���̂Ȃ�A�n���ɑ��ĉ��肵�Ă݂Ă��悩�����͂��ł��B�l���Ƃ��Ă͂���ۂǂ��ꂪ���ʂł��傤�B�������Ȃ������̂͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@�@�@�@
�s�K�Ȃ��ƂɁA�b���R�O�q���̌��]���x��n���͂��ɂ�������炸�A�����͂������̒l��������A���̗��R�Ƃ��Ă��������������ꂽ�g�������͏k�݁h�A�^�������ɂ���āg���Ԃ̐i�ݕ����������h�Ƃ�����Ŕ�Ȋw�I�Ȑ����̂ق����A�����ɂ��ʔ������ň�ʎ���������ł��B�_�Ȃ�ʐl�Ԃ̔߂��������̂����ł���܂��B�������l�����͂����炭���̂悤�ł��B
�����𑪒肵���}�C�P���\�����O��Ƃ��Ă�������Ƃ�g���Đ\���܂��ƁA�ԃm�b�g�ő���D���̏�ŋʂ�]�����A�D�̐i�s�����Ƃ��̋t�����Ƃł͋ʂ̑����͈Ⴄ�ł��낤�A�Ɨ\�������̂Ƒ債���Ⴂ�͂���܂���B�ʂ̑������ǂ̌����������ł��������ƂɊw�҂����͋V���Ă��܂����A�z��������ΈÂ��Ȃ�̂Ɠ������炢�ɓ�����O�Ȃ��Ƃł��B
�@��������ǂ�ȂɊ��ɑD�̍b�Ɏ��t���悤�ƁA�䂪�����Ȃ�A�ʂ̑����͂ǂ̌����ł��ς��Ȃ��̂͑D��̒N���������Ă킩��܂��B�܂�A�ʂ��]�������}������b�͖ڂɌ����܂����A�n���������̃G�[�e���Ȃ�d�͏�͌����Ȃ������ɉ߂��܂���B�ʂɂƂ��Ă̍b�ɂ�������̂́A���ɂƂ��Ă͏d�͏�ł���̂��ƁA�ڂ������͋C�Â��Ă��܂��B
![]()
���Ƃ��܂��ƁA�n���̏d�͏ꂩ�痣�ꂽ�F����ԂŁA�����}�C�P���\���������s���A���̑��u�͑��z�n�ɖ����Ă��鑾�z�̏d�͏�ɑ��Č��]�^�������Ȃ���A����ǂ͊ԈႢ�Ȃ������ɏ]�������̑��Α��x���ϑ������ł��傤�B�c��Ȏ��ʂ����n���̏d�͏�Ƃ͈���āA�ϑ����u�̎���ɂ��鎩�g�̏d�͏�͖����ɓ������i���L���͌W���͂���߂Ĕ���Ȃ��߂ł��j���炢�ł�����B
�@�킽���͂��̌��؎������ʂ̐��ۂ��ꖕ�̕s���Ƒ傫�Ȋ��҂������A���������������ׂ��]��ł��܂����A���̂Ƃ�����s���悤�Ƃ��������͌����܂���B�����ُ̐��͂ǂ̗��n��w�ł��ǂ܂ꂽ�͂��ł����A�����Ƃ��������Ȃ��̂́A���̂܂܌������̈��ׂ��ێ��������w�p�E�̎K�т����ؖ�������̂��A�Ǝv�������Ȃ�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i013/11/6�j